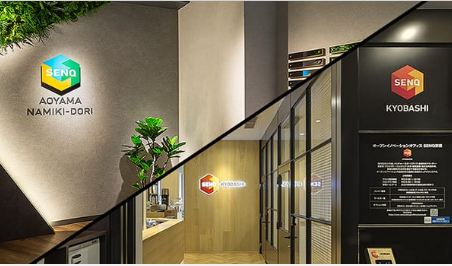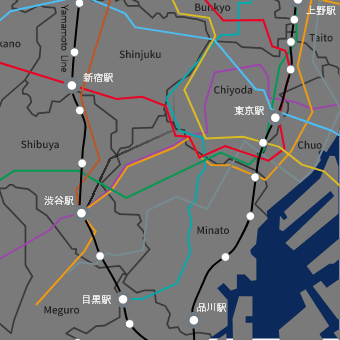飲食店で、利用客が自分のスマートフォンを使ってテーブルオーダーや決済を行える、クラウドPOSシステム「ZEROレジ」を展開するXERO株式会社。代表の小沼 亮(こぬま りょう)さんは、「今は『レジ』だけれど、将来的には『飲食店全体をテクノロジーで支援する』サービスを提供したい」といいます。今回は小沼さんに、サービス開発のきっかけや今後の展望について伺いました。
-----ご経歴と、XERO株式会社立ち上げのきっかけを教えてください。
小沼:新卒でNTTドコモに入社し13年ほど勤務した後、株式会社ピアズに転職しました。マザーズ上場を機に新しいビジネスモデルを創るということで、新規事業担当としてジョインしました。XERO株式会社は、そこで立ち上げた新規事業「ZEROレジ」を運営するために、ピアズの出資を受けて設立した会社です。ピアズとXEROはビジネスの成り立ちがまったく違うので、同じ事業体の中でやるよりは、新しい会社で新たにメンバーを集めたほうが成長できると考えてのことでした。
-----「ZEROレジ」について、教えていただけますか。
小沼:ZEROレジはクラウドPOSシステム、一言でいえばタブレット端末を使った飲食店向けのレジです。特徴は、利用客が自分のスマートフォンを使って非接触でオーダーや決済ができる機能ですね。利用客によるアプリのインストールなどは不要で、店頭でQRコードを読み込めばすぐに使えます。店内でのテーブルオーダーに加えて、テイクアウトやデリバリーにも対応しています。
キャッシュレス化もそうですが、このタイプのソリューションは中国やアメリカで先行して広まっていました。一方、日本では旧来のPOSシステムから転換が進んでいなかった。つまり、レジと予約管理や売上管理、経理といったシステムが分断されたままで、ひとつに統合されたソリューションになっていません。それでは働いている方々も大変だし、だからこそ、そこにビジネスチャンスを感じたわけです。
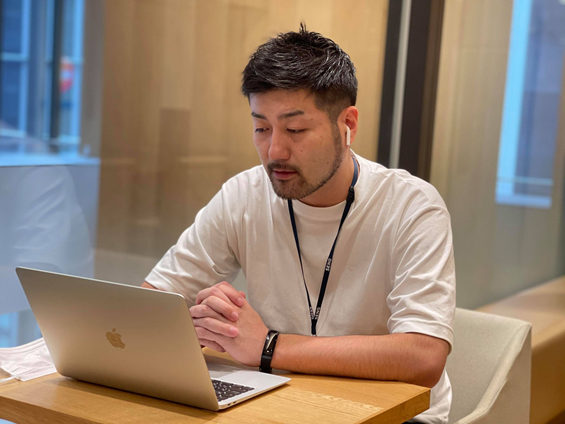 -----開発を始められたのはコロナ禍以前とのことですが、今や感染症対策にもなるとあって、引く手あまたなのではないですか。
-----開発を始められたのはコロナ禍以前とのことですが、今や感染症対策にもなるとあって、引く手あまたなのではないですか。
小沼:そうですね、2回目の緊急事態宣言以降はお問い合わせもかなり増えました。ただ、導入はスムーズに決めていただけても、実はその後のアフターフォローが大変なんです。
接客を担当する方のITリテラシーは店舗によってまちまちですから、僕たちが自ら店舗へ行って、OJTのようにサポートしながらオペレーションを覚えていただいています。北陸地方のフードコートに導入していただいた時は、スタッフが3週間泊まり込みで店舗に通いました。でも、フードコートではZEROレジがいわゆる「呼び出しベル」代わりにも使えるとあって、その後の評判は上々でしたね。
-----注文品が用意できた時に、自分のスマートフォンにお知らせがくるのですね。それは便利です!他にはどのようなユーザー様が利用されていますか。
小沼:取引先としてはいわゆる個人経営の店舗が多いのですが、全国展開するチェーン店で導入いただいていることもあり、店舗数ではそちらのほうが多いかもしれませんね。
個人経営の店舗では「利用客のスマートフォンでオーダーや決済ができる」という基本的な機能だけでも重宝されています。一方でチェーン店を運営する企業では、公式アプリとの連携やポイントプログラムとの連携、会員情報・注文情報・決済情報を紐づけたデジタルマーケティングといった目的で開発も承っています。
 -----XEROが入居されている SENQ京橋の印象はいかがですか。
-----XEROが入居されている SENQ京橋の印象はいかがですか。
小沼:もともと、一般的なオフィスではなくコワーキングスペースに入居したいと考えていました。交通の便が良いところで、食に携わる人も含め、いろいろな人との出会いがあるような……というくらいで、そこまで明確な条件があったわけではないのですが、COOの木村がSENQ京橋を見つけてきてくれて「ここだ!」と。
-----“交通至便”と“食”を両立しているコワーキングスペースはなかなか珍しいですからね。
小沼:それに、インテリアや設備もきれいだし、24時間365日出入りできる。入居してから、マネージャーに近くの銭湯も教えてもらって「これは快適だな」と。会社としてはリモート勤務もできるようにしていますが、僕は毎日オフィスへ来ています。
イベントに積極的なところも入居のきっかけになったので、オンラインイベントも、状況が落ち着いたらオフラインのイベントも、どんどんやってほしいですね。
-----今後の展望について聞かせてください。
小沼:先ほどもお話しした通り、飲食店の大きな課題のひとつは「システムの分断」だと思っているんです。店舗の中はもちろん、利用客とつながるシステムも分断していて、使いづらかったりする。
ZEROレジはInstagram連携ができるのですが、それはこの分断を解消したかったからです。利用客がInstagramで店舗の料理写真を見て「おいしそうだな、食べたいな」と思ったらすぐ注文ページへアクセスし、注文、決済まで完了できる。さらに店頭やテイクアウトをして料理を食べた後は、その写真をまたInstagramにあげて、誰かがそれを見る……という一連の流れでデータを連携させていくことができます。こうしたフロントサイド側の連携や、そこから生まれる連鎖がとても大事だと考えています。
もちろん、先ほど話に出たレジと予約管理や売上管理の連携、つまりバックエンドの連携も重要です。僕らがこのフロントエンドとバックエンドのシステムをしっかりつなげば、「この時来店した利用客はこの店をどう評価しているのか」といった分析もでき、店側が1人ひとりの利用客にしっかり向き合っていける。そういったことがフレキシブルにできるような形を創っていくのが、僕らの今後だと考えています。
-----その形を創るための“打ち手”として、考えていることはありますか?
小沼:飲食店を経営したいですね。そこを自社製品のモデル店舗のような場にして、ZEROレジだけでなく、例えば配膳システムなどもパッケージで取り扱っていく。
経営側で飲食に携わったことがないメンバーが多いので、実際に店舗経営をすることで飲食店側の痛みも苦しみも知って、利便性もしっかり追求しながら形づくっていきたいです。
それに、お客様に実際にモデル店舗を見に来ていただければ、製品の魅力はもちろん僕たちがやりたいことも一番伝わりますから。店舗ができたら、SENQでも取材にきてくださいね!
------取材はもちろん、SENQのスタッフや入居者とみんなでランチに行きます!イベントの打ち上げもさせてください!本日はありがとうございました。
(ライター:丸田カヨコ)※掲載内容は取材当時のものになります。