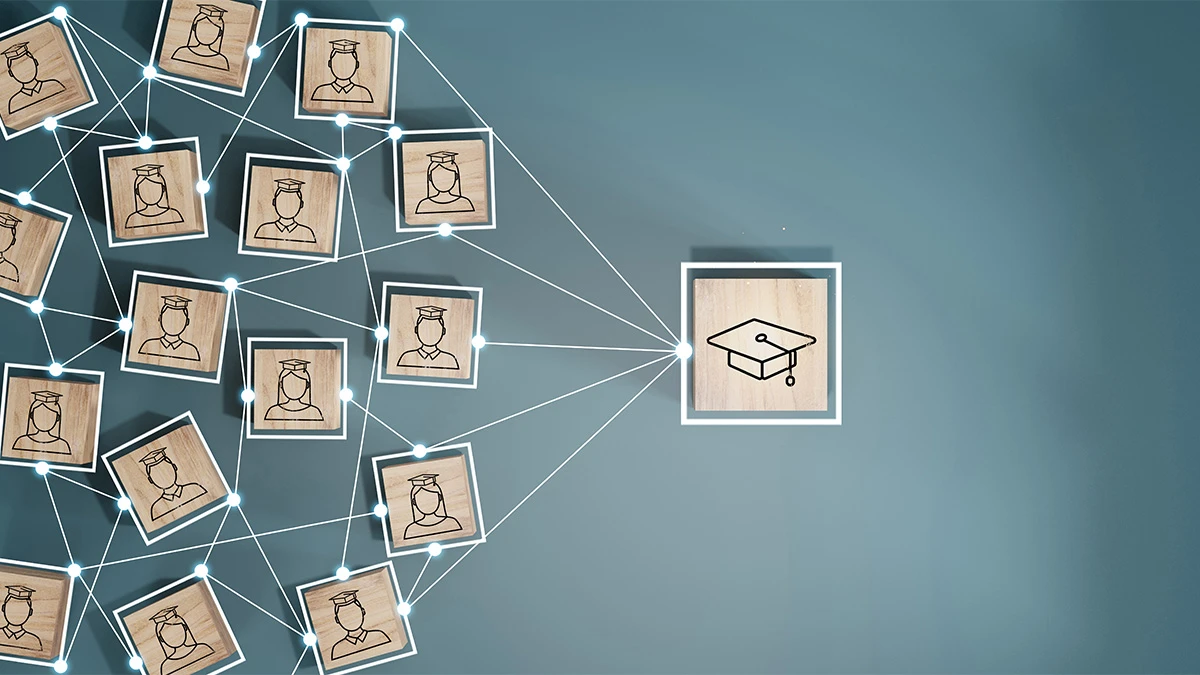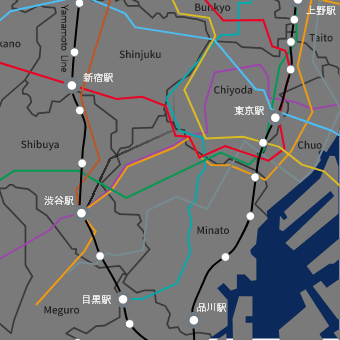次世代の働き方、ハイブリッド勤務とは
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、多くの企業が急遽、リモートワークに切り替えました。その後、緊急事態宣言が解除された後も、オフィス勤務とリモート勤務を使い分けるハイブリッド勤務を採用する企業が増えています。ハイブリッド勤務を採用することでオフィスの固定費を見直すきっかけになったり、社員のワークライフバランスが改善されたり、さまざまなメリットがあります。その一方で、IT環境の整備をはじめ、考えなければならない課題も多数存在します。これからハイブリッド勤務を始める企業は、いったい、どの点に気をつければ良いのでしょうか。実践的な観点から考えてみましょう。
急速に増加する「ハイブリッド勤務」とは?
各企業が、真の働きやすさを追求し始めている
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、急速にリモートワークが拡大しています。企業によっては早くもオフィスを縮小し、社員にリモートワークを推奨しているところもありますし、先進的な企業のなかには、リモートワークが効果的に機能していることから、「オフィス不要論」も出始めています。
新型コロナウイルスの感染終息の糸口が見えないなか、今後もこの傾向は続くと見られています。
そんななか、急激に増えているのが「ハイブリッド勤務」というワークスタイル。これは、業務の多くをリモートワークでこなし、週に1~2度オフィスで働くというスタイルで、その名の通り、「オフィス出社」と「自宅でのリモートワーク」の利点を掛け合わせた働き方です。
例えば、「月曜日と金曜日を出社指定日として部署ごとに分散出社を行い、火曜日~木曜日はリモートワークを推奨する」という企業や、「毎月1週目と4週目はチームごとに1日出社とし、2~3週目はリモートワークを行う」という企業など、出社スタイルは企業によってさまざまです。
もちろん、コミュニケーションを円滑にするために、出社日以外はZoomなどのアプリケーションを活用し、オンラインでのミーティングをこまめに実施。また、取引先との打ち合わせ等は、先方の事情に配慮しつつ柔軟に対応している企業もあります。
いずれにしても、週5日の出社を当然のものとしていた既成概念にとらわれず、出社勤務のスタイルを自由にアレンジし、真の意味で社員にとっての働きやすさを追求することを本格的に模索し始めているのは、どの企業も同様のようです。
「ハイブリッド勤務」はなぜ、企業の生産性を高めるのか
リモートワークは個人のスキルを向上させる
こうしたハイブリッド勤務を選択する企業が増えているのは、もちろん、この働き方のスタイルが企業の生産性を高めるため。それではいったいなぜ、ハイブリッド勤務が企業の生産性を高めるのでしょうか。その理由を考えてみましょう。
(1)固定費削減に伴う余剰予算を生産性向上につながる資源に投下できる
ハイブリッド勤務を採用している企業のなかには、社員の60〜70%分の席だけ用意すると決め、固定席を廃止し、フリーアドレス制に切り替えた企業などもあります。
オフィススペースの削減により、オフィスの賃料を見直し、固定費を割愛することで、他の部分へ資源を投下し、生産性の向上につなげることができます。
(2)社員のワークライフバランスが見直され、定着につながる
すでにハイブリッド勤務を採用している企業では、「引越しを考えている」という社員が目立っています。これは、「会社の近くに住む必要がなくなり、子育てに最適な環境を最優先したい」「自宅のテレワークスペースを確保したい」という社員が増えているため。
つまり、ハイブリッド勤務は、社員にとってワークライフバランスを考えるきっかけになっており、ひいては、社員の定着を期待することができるのです。
(3)さまざまな働き方で柔軟に業務をこなす能力が身に付く
業種によっては、ハイブリッド勤務が難しいものもあります。一般に、リモートワークと相性がいいのはプロジェクト型のマネジメントとされており、プロジェクトメンバー1人ひとりが主体的に動くのは、オフィスに出社してもリモートワークになっても変わらないため、それほど困難なくリモートワークに移行できるとされています。
また、デジタルトランスフォーメーション(DX)が推進されている企業もスムーズにリモートワークへ移行できるでしょう。しかしその反面、接客販売や医療福祉関係など、対人対応が前提の業務はリモートワークに向いていないとされています。また、製造業のように大掛かりな機械を用いるような業務も、リモートワークには不向きかもしれません。
しかし、こうした職種でも工夫によってハイブリッド勤務に切り替え、さらにパフォーマンスを向上している企業もあります。
大事なことは、社員1人ひとりが自主的に業務を遂行する意志をもち、円滑に業務を進めるために工夫すること。与えられた仕事を淡々とこなすだけでなく、オフィス出社とリモートワークの利点を各自が考え、行動する力を身に付けることで、結果的に生産性の向上が期待できます。
(4)コミュニケーションスキルが向上する
毎日オフィスに出社する必要がなくなるということは、社員同士が顔を合わせる機会が少なくなるということ。その分、オンラインを通したコミュニケーションなどを活発に行う必要があります。
対面しないオンラインでのコミュニケーションは、雑談がしづらい、相手の間を取りにくい、意図したことを伝えづらい、場の空気感を読みにくいなどの難しさがあります。
しかし逆に考えれば、コミュニケーションが難しいということは、それだけ意思疎通のスキルが向上するということ。実際、リモートワークに移行したことで、「コミュニケーション不足を補うために、意思を伝えるスキルが向上した」という意見も多く聞かれます。
「ハイブリッド勤務」を実現するために必要なこと
IT環境と勤怠管理に配慮。必要に応じてシェアオフィスの活用も
ハイブリッド勤務を実現するうえで1番の困難は、IT環境の整備です。実際、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、急遽リモートワークに切り替えた企業のなかには、IT環境を整備する時間がなかったため、社員の家庭環境によってはWi-Fiが整っていないなど、解決すべき課題もありました。
そのため、ハイブリッド勤務を考えるためにはまず、IT環境を確実に整備することが必要になります。社員にモバイルWi-Fiやノートパソコンを支給して、すべての社員が平等にワーク環境を整えることができるよう、十分配慮することが必要です。
また、情報漏洩のリスクへの対処も、考えなければなりません。セキュリティー問題への対策方法はさまざまなことが考えられますが、「情報漏洩を防ぐためのシステムを導入する」「リモートワーク用の就業規則を作って社員に徹底する」「情報に需要度のランクをつけ、情報にアクセスできる社員を制限する」などが挙げられます。
さらに、社員の勤怠状況を管理するため、新たなシステムを導入することも検討する必要があります。リモートワークでは、社員の勤務時間を管理することが難しいため、社員の人事情報をまとめたり、労働状況に応じて給与を決定したりすることが困難になります。必要に応じてオンラインでの勤怠管理システムを導入するなど、対策が必要になるでしょう。
そして、自宅での作業が難しい社員には、コワーキングスペースを提供することも考えると良いでしょう。多くのシェアオフィスは法人に対してさまざまな会員制度を用意しているため、目的に応じて最適な契約スタイルを選ぶことができます。社員に対してワーク環境を提供するだけでなく、「本社のスペースを縮小し、会議室を利用する時にはコワーキングスペースを活用する」という使い方もできるので、ハイブリッド勤務の導入にあたっては、コワーキングスペースの利用を積極的に考えるのもおすすめです。
SENQの法人向けプランでは、企業のニーズに合わせて柔軟にプランを組むことが可能です。企業で利用するコワーキングスペースを検討の際は、ぜひ内覧予約をしてみてくださいね。
(ライター:鈴木博子)