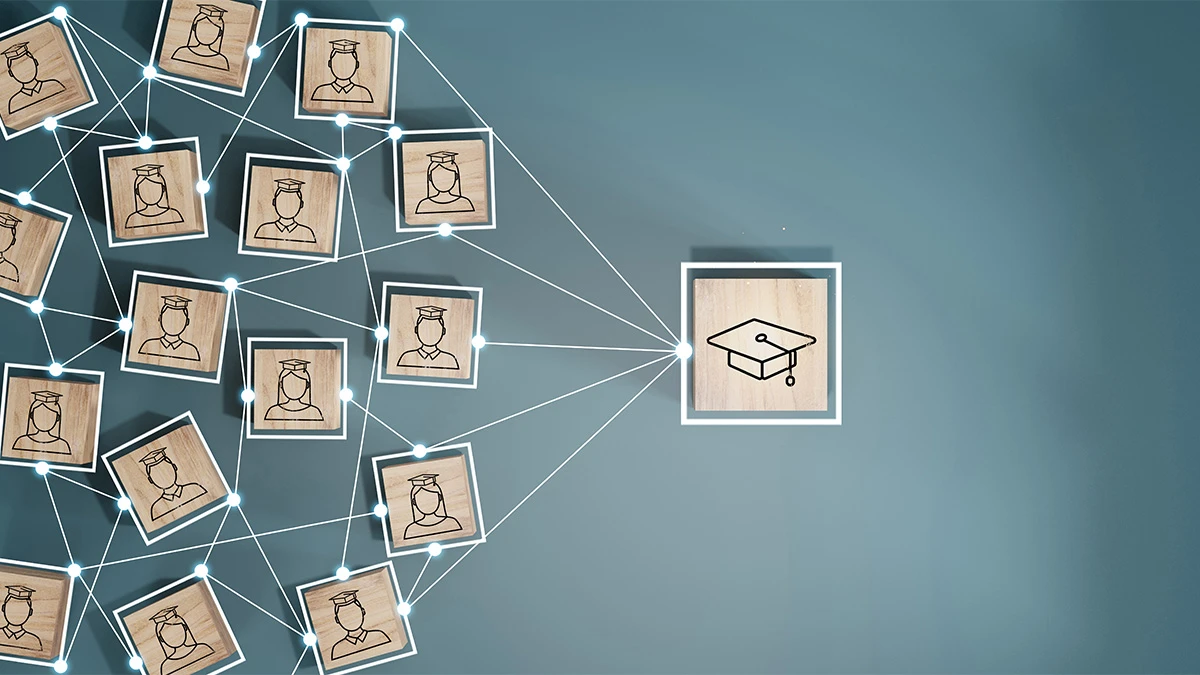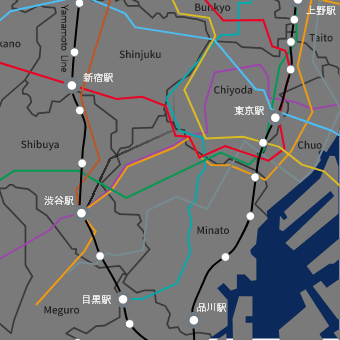起業3年目からの生き残り術
「起業から〇年生き残れる企業は○%」といった「企業の生存率」が厳しいことは、どこかしらで耳にしたことがあるのではないでしょうか。その多くは「起業から1年」または「10年」といったタームで語られます。しかし、経営者として注目しておきたいのは、実は「起業3年目から」。厳しい時期を乗り切ったように見えるこのタイミングこそ、一層シビアに経営に取り組むべきなのです。
今回は、起業3年目を迎えた人、迎えようとしている人はもちろん、これから創業を考えている人も、来るべき3年目を見据えて考えておきたい内容をまとめました。
なぜ「3年目から」なのか?
では、なぜ「3年目から」の生き残り術が必要なのでしょうか。
開業前からの準備資金が尽きはじめる
起業にあたっては、しばらくまとまった利益が出なくても会社と事業を存続させられるよう、準備資金を用意するのが一般的です。1人社長でも最低1年分、できれば3年分は準備しておきたいと言われています。そう、3年目はこの準備資金が尽きてくるタイミングなのです。
事業拡大に踏み切る好機でもある
大きな損失を出すことなく堅実に事業を継続している会社であれば、3年目はこれまでの実績を足場に事業を拡大する好機でもあります。1年目は夢中で、2年目は前年越えを目標にと進んできて、ここでモチベーションを保つには、新しい目標が必要なのです。
そもそも「3年」は中期計画に適したターム
「起業から3年」に限らず、会社にとって「3年」は中期計画に適したタームです。これまでの事業を振り返り、経営理念を見直し、今後3年はどのように進んでいくかを見定める……となれば、必然と生き残るための策を練ることにもなります。
「資金調達」が生き残りのキモに
起業3年目から生き残っていくためのポイントは、やはり創業期からの課題とされる「資金調達」にあると見られます。
半数以上のスタートアップが「資金調達」を課題としている
「中小企業白書」(2017年度)によると、会社創業期の課題としては、会社の成長スタイルに関わらず半数以上が「資金調達」を挙げています。また同白書では、高成長型の企業でも安定成長型の企業でも、借入れにおける課題として「融資を受けられなかった」が最も多く挙げられています。
その後、成長初期~安定・拡大期の課題としては「質の高い人材の確保」が目立ってきますが、資金繰りが安定しなければ、人材確保にコストをかけることもできません。
早めに固定費を抑えておくなどして、手元の資金を厚めに
融資を受けられない、計画通りの利益がなかなか出ない場合には、例えばいち早く家賃・設備・人件費など会社にかかる固定費を見直し、出ていく費用から調整する習慣をつけましょう。借入れできる時は思い切って多めに借り、切羽詰まる前に手元の資金を増やしておくことも重要です。いずれにしても厳しい状況ではありますが、これを乗り越え、長期にわたって安定した経営を目指しましょう。
3年目以降を生き残るための術とは?
コストカットや融資よりももっと根本的な生き残り術としては、やはり経営者としての目利きがモノを言います。といっても、勝負勘ばかりではありません。つぶさな情報収集と的確な分析で、確実に見極めることが基本です。
市場を見極める
創業期は「一山当てる」よりも、「確実に利益を出していく」市場を見極めましょう。競合のないニッチ市場でスモールビジネスを回す、営業や技術者をそろえて受託事業で手堅く稼ぐ……、こうした市場で会社に体力をつけていきます。
創業メンバーを見極める
夢を持って共に起業したメンバー同士が、会社の浮き沈みにつれて意見が合わなくなってもめてしまったり、裏切りにあって情報や資産を持ち出されたり、といったケースは枚挙にいとまがありません。厳しい時期を乗り切れる相手であるか見極めるのはもちろん、信頼し合っているからこそ、法的拘束力のある取り決めをしておくことも重要です。
事業拡大の時期・規模・方向性を見極める
起業3年目は事業拡大のチャンスでもありますが、足元が見えていない急激な多角化や増員、回収の見込みが甘い設備投資、固定費が大幅に上がるような事務所移転など、無理のある拡大路線はおすすめできません。目標を高く設定することは悪いことではありませんが、そこへ向かうコースはあくまで堅実でありたいところです。
メンターや起業家のアドバイスを受けやすい環境に
経営者として見極めの難しい判断を求められたとき、同じ目線で相談に乗ってくれる人がいたら心強いのではないでしょうか。SENQでは、各界のトップ企業やベンチャーキャピタルなどで豊富な経験を持つ多くのメンターを迎えて、起業家へのアドバイスなどを実践しています。また、入居者同士の交流会なども、全拠点で毎月実施中です。先輩の声を聞き、同じ起業家として良き仲間と知り合える機会を持ちませんか。