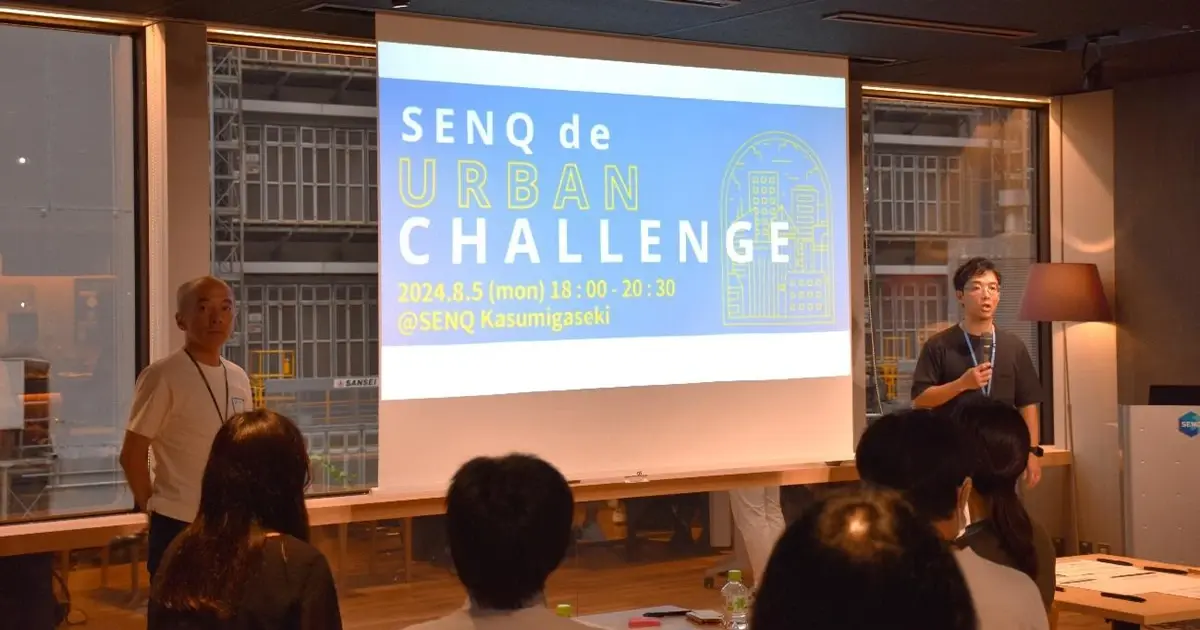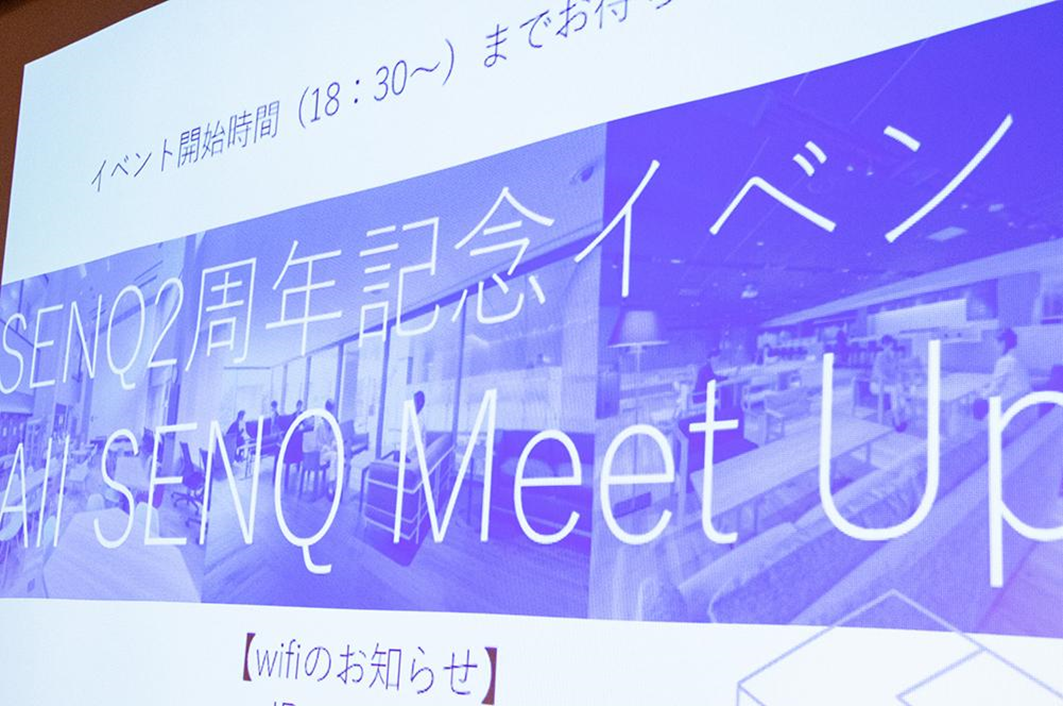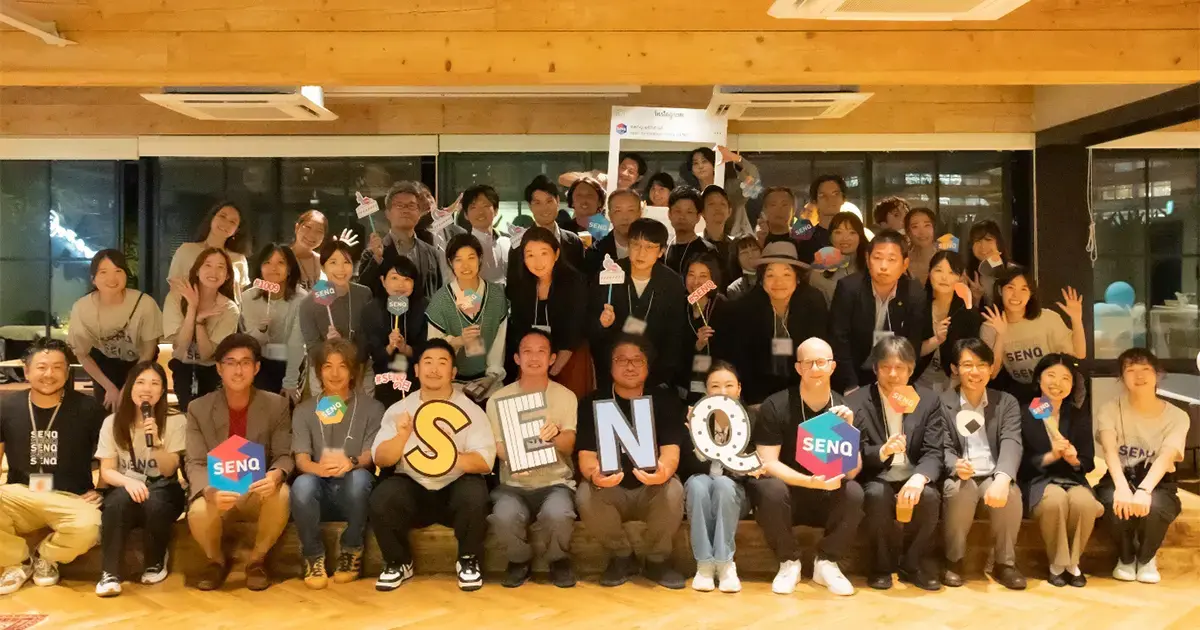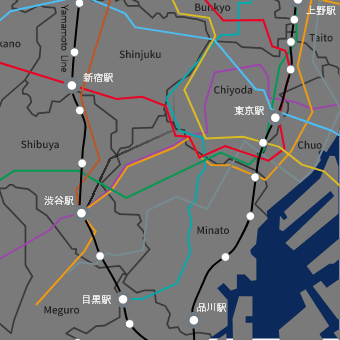「デザインとテクノロジーの力で既成概念を打ち破る共創の場」ことSENQ六本木。ここで10月30日、個人投資の世界に新風を吹き込む日本クラウドキャピタルの経営陣が、書籍『起業の科学 スタートアップサイエンス』(日経BP社)で知られる株式会社ユニコーンファームCEOの田所 雅之氏をゲストに迎え、スタートアップとエンジェル投資について語りました。
ーープログラム
【第一部】日本クラウドキャピタルの新規事業戦略について
【第二部】トークセッション
田所 雅之氏に学ぶ、スタートアップ企業の見極めポイント
ゲスト :株式会社ユニコーンファーム CEO 田所 雅之 様
モデレーター:株式会社日本クラウドキャピタル CEO 柴原 祐喜 様
ー「FUNDINNO」が創る、株主コミュニティが非上場株式会社を支援するシステム
第一部では、非上場株式会社の現在抱える課題に関する説明と、その解決策として、柴原さんから日本クラウドキャピタルが運営する株式投資型クラウドファンディングサービス「FUNDINNO」と、事業計画書作成サービス「FUNDOOR」が紹介されました。
家計から非上場株式会社への投資機会を定着させ、IPOやM&Aよりもタームや目標設定が小規模な「株主コミュニティ(非上場株売買)」を作るというビジョンに、客席からも熱い視線が送られます。

写真:柴原 祐喜 様
ー失敗を99%防ぐには「まずプロダクト」ではなく「先に営業資料」を作るべし!
第二部は、これまで日本と米国シリコンバレーで合計5社を起業してきたシリアルアントレプレナーであり、現在は国内外のスタートアップの戦略アドバイザーやボードメンバーを務めながら、日本最大級のウェブマーケティング企業こと株式会社ベーシックのCSO、株式会社ユニコーンファームのCEOを兼務する田所 雅之様にお話を伺うことに。日本クラウドキャピタル CEOの柴原 祐喜様がモデレーターとなって、鋭い質問を投げかけました。
まずは田所さんの自己紹介からの流れで、スタートアップからIPOまでに予測される20のリスク・オポチュニティを挙げた「チェックリスト」が示されます。
例えば、プレシード期のリスクとしては「課題を見つけることができるか」、「あるべきソリューションを検討できるか」、「創業者と課題が合っているか」、「初期の資本政策リスク」といった項目が並びます。
続くシード期は「プロダクトをローンチできるか」、「人が欲しがるものを作れるか」など。シリーズA期には「継続して刺さるプロダクトを作れるか」、「人を採用できるか」、「起業家から経営者になれるか」といった、安定経営のための項目が登場してきます。
IPOを控えたシリーズB期には「ポートフォリオ経営をしたときに事業間のシナジーがあるか」、「IPO前のダウンラウンドに耐えうるか」、「上場後に成長するための仕込みがあるか」などの項目が、ステップアップへの着実な助走を想起させます。

こうしたリスクを見出す一方で、田所さんは著書『起業の科学 スタートアップサイエンス』で「失敗の99%は防ぐことができる」と訴えています。そこで、柴原さんはこの「失敗を防ぐメソッド」について質問しました。
田所さんはまず「なぜ失敗するかというと、まさにチェックリストに挙げたことです。(リスクを乗り越えられずに)人が辞める、やる気をなくしてしまう、お金が尽きる」といいます。そして、その元凶は多くのスタートアップが「いきなりプロダクトを作ってしまう」ことと「全方位的に売ろうとする」ことにあるという持論を示しました。
「僕が(スタートアップの)支援を始める時は『プロダクトを作れ』とはひとことも言わない」と田所さん。なんと、営業資料を作るのが先だというのです。
まずターゲットカスタマーを見出し、それに対する勝ち手を考え、仮説を立てるために、営業資料を作ってヒアリングをする。「どんなものが欲しいか、幾らだったら買うのか」を聞き出してから本格的にプロダクトを組み立て、「買う気がない人に売ろうとする」ことを止めると、リスクは減る……というわけです。
これには柴原さんも「まさに重要であり忘れがちなところ。いきなりアイデアを思いついて、すぐに投資に走るんですよね。やりたい気持ちが勝って、ニーズがあるかないか見極めるのを忘れてしまう」と絶賛します。
続く質問は、これも田所さんが掲げる「課題を自分ごとにしなければならない」というノウハウについて。これは、田所さんのメソッドと同じ手法で課題を解決していった「クラウドワークス」の事例を基に解説されます。
2年9か月でIPOに至った同社ですが、初期の戦略に投入した資金はたったの5万円。
その戦略とは「ハッカソンにスポンサーとしてピザを提供することで、マッチング事業の重要な要素である『優秀なエンジニア』との関係を広げる」ことでした。こうして知り合ったことをきっかけに凄腕のエンジニアが集まり、その様子を見てさらにエンジニアが集まってくるというわけです。
さらには、同社もまずプロダクトを作るのではなく「ランディングページ(LP)だけ作って、マッチングサイトが完成する前に営業に行った」といいます。そして、先の戦略で手に入れたエンジニアのリストを切り札に、ローンチ前に法人顧客30社を獲得するに至りました。
マッチングサイトは一見、登録職種のバリエーションの広さが魅力のように見えますが、同社はまずターゲットを「プロのエンジニア」に絞り込みました。「広げすぎると、起業のニーズとマッチングしない」ことに気づいていたのです。
柴原さんはこの事例をGE社のCEOだったジャック・ウェルチの手法になぞらえ「いかに立ち上げ当初から『選択と集中』を実践できるかが重要」だとまとめました。

写真:田所 雅之 様
ーー成長できるスタートアップには「ゴレンジャー」が揃っている!?
柴原さんからは続いて「いきなりモノづくりをせず、課題検証をすることはどれほど大事なのか」と、話題の中心をさらに深掘りする質問が投げかけられました。
田所さんは、課題検証の重要さを、野球の打撃になぞらえて説明します。「スタートアップの事業は実験であり、実験で大切なことは『打席に立つ回数』なんです。市場調査を踏まえての試作なら、ある意味何回でも打席に立てる。でも、いきなりプロダクトを作ってしまったら1打席で終わってしまう」。
ここまでスタートアップ側に立った話題が続きましたが、最後はエンジェル投資家へのアドバイス。「エンジェル投資家が、成功する企業を見極めるポイントは」という質問に、以下のような見極め方が挙げられました。
- 「そもそも解決しようとしている課題は何か」という質問をする
- 「プロダクトの価値がユーザーに刺さっているか」を見る
- 創業期の決め手は「人」なので、創業者に「なぜあなたである必要性があるのか」聞く
- お互いを補完できる人員構成かを見るために「どういうチームを組成しているか」を聞く

チームの組成については、客席からも「集まっているメンバーのどこに着目するか」という質問が投げかけられます。田所さんは「成長できるスタートアップは『ゴレンジャー』を組成できている」と、以下の通り優秀なチームを戦隊ヒーローに例えました。
アカ :リーダー(CEO、CCO)
アオ :冷静なエンジニア
キ :人事周り(HR)のスペシャリスト、ムードメーカー
モモ :デザインのHipstar
ミドリ:成長戦略を立てることができる参謀
最後に客席から「自分は事業継承した2代目で、自社は安定運用しているがブレイクスルーできない。(田所さんは)斬新なアイデアがない企業にどう対応しているか」という質問が寄せられました。
ここで田所さんが挙げたのが、執筆中の著作のテーマでもあるという「三階建て型組織」(コアビジネス・新規事業・イノベーション)です。
「イノベーションの仕事は、既存の事業から分離して組織しなければならない。 」というドラッカーの言葉を挙げ、PL(損益計算書)のみで評価する旧来の組織では、新規事業を潰してしまいかねない……と訴えます。
まだ世に出ていない書籍からの貴重な情報ですが、田所さんは「今の資料欲しい人はメールください、出版社に怒られるかもだけど!」と会場中を笑わせ、トークセッションはなごやかに締めくくられました。
スタートアップのメンバーにも、エンジェル投資家にも響く名言が数多く飛び出したこのイベントもまた、99%失敗を防いで(!?)の盛況となりました。起業は不思議なマジックではなく、一つひとつに根拠があるサイエンスなのだと、あらためて感じた参加者も多かったのではないでしょうか。
❖ 今回のご登壇企業 ❖
株式会社ユニコーンファーム : https://www.unicornfarm.jp/
株式会社日本クラウドキャピタル : https://www.cloud-capital.co.jp/
SENQ六本木では、これからも、「デザインとテクノロジーの力で既成概念を打ち破る共創の場」に相応しいイベントを定期的に開催してまいります。
(ライター:丸田カヨコ)